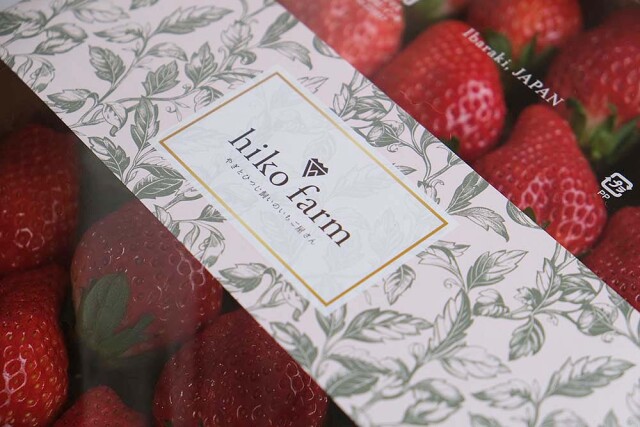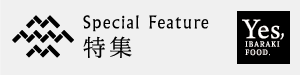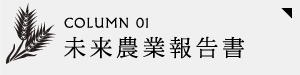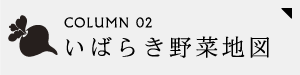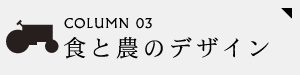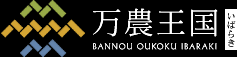脱サラをして鉾田市のイチゴ生産者「村田農園」にて研修を積み、2021年に常陸大宮市にて自らの農園を立ち上げた彦田夫妻です。
妻の結衣さんがデザインしたショップカードやインフォメーションには「hiko farm」の名に添えて、「やぎとひつじ飼いのいちご屋さん」と書かれています。実際に大きな柵をめぐらして数頭の山羊と羊を飼っており、それはお二人の思い描く農園のイメージを象徴しています。
直売所にしている古いトレーラーハウスにはアンティーク調のカウンターや自転車、飼っている羊の毛から紡いだ糸などがディスプレイされて、まるで輸入雑貨のショップのようです。イチゴの配達に使っているのはアメリカフォード社製のヴィンテージトラック。前のオーナーはカリフォルニアのワイナリーで、車体に描かれたロゴや傷をあえてそのままに残し、エイジングを魅力として楽しんでいます。トータル、とてもお洒落。牧歌的でありながら洗練されたセンスを感じる、独自の世界を創造している彦田夫妻。お二人ならではの価値観やものの見方、目指す方向があるのだろうとお見受けしました。

なにが一番たいせつか 自問の先に見つけたこたえ
−以前はIT商社の技術営業のお仕事をされていたとのこと。かなり思い切った方向転換ですが、なぜ農業への転職を決意されたのか、その動機と経緯を教えてください。
真吾さん:
農業をやろうと思った一番の理由は、もっと家族といる時間を増やしたかったからです。以前の仕事は国内外を飛び回る出張の多い仕事で、朝は子どもが寝ているうちに出かけ、夜は寝た後に帰宅。妻とも短い時間しか顔を合わせられません。頭の隅で転職を考えていた頃、農業市場向けの技術提供で、茨城県内の農家さんを訪れるようになりました。その時の最初の訪問先が鉾田の村田農園さんでした。
実は僕は心臓に持病がありまして。発覚したのは20歳頃です。経過観察をするうちに2016年、そろそろ手術をしましょうという段階になりました。成功率は高かったのですが、それにしても全身麻酔で胸を開き、一度は心臓を止めて人工心肺に繋げるというようなオペでしたので、万一のことも頭をよぎりました。結婚してちょうど1年くらいで、息子がお腹にいるようなタイミング。あらためて自分の人生を見つめ直す機会になりました。
幸せってなんだろうね、というような話を妻ともたくさんして。僕らにとっては一緒にいられることが一番の幸せなのかもしれないと思いました。たとえばカフェを開くとか、そのための方法は他にもあったと思いますが、ちょうどそういうタイミングで出会った村田さんと、村田さんの作るイチゴが、今の仕事に就こうと思ったきっかけになったと思います。
−ご夫婦共に農業とはまったく縁のない家庭で育ったということですが、農家の皆さんからはどのような影響を受けましたか。
真吾さん:
生まれて初めて農業という世界に触れたところが村田農園さんでした。村田さんという人の魅力にもひかれましたし、最初に食べさせてもらったイチゴの印象が衝撃的でした。なんだこれは!と理解が追いつかないくらい、イチゴの全ての要素が凝縮して詰まっているようで、ものすごくおいしかったんです。後に村田さんの元で農業を学びたいと思ったのは、この時の経験が大きかったと思います。
他にも同じくイチゴ農家さんで、ご自身の趣味に時間とお金をかけて私生活をとてもエンジョイしている方がいました。経営の仕方によっては自分の好きなライフスタイルが実現できるんだと希望を感じました。
結衣さん:
仕事とプライベートを混同するのを嫌う人もいると思いますが、私たちの場合は今もイチゴ作りが仕事という感覚があまりないように感じています。始めてみたら二人とも、イチゴを育てることが今までの仕事の中で一番好きだったんです。これはすごいラッキーなことですよね。羊たちの世話を含め毎日好きなことをやっている感じで、ワークとライフがミックスされている。だから毎日が楽しいんです。
−未知の世界に飛び込むことに不安はありませんでしたか。また研修期間中、仕事はどのように覚えていきましたか。
真吾さん:
完全にスキルゼロからのジョブチェンジですから、もちろん不安はありました。脱サラを考え始めた時に息子は0歳。不安だらけでしたが、なんとか自分に言い聞かせていたのは、最悪ものにならなくても東京に戻ってなにかしら仕事は見つかるだろうと。そう思って踏み切りました。
そもそもは前職の仕事のために農業のことをもっと知りたいという思いから、毎週土曜日に東京から村田さんのところへ通って仕事を教えてもらっていたんです。摘み取りやパッキングの手伝いをさせていただきながら村田さんとの会話を重ねていく中で、農家になる夢が具体的になっていきました。その期間が1年半ほど続き、修行をするならここだと気持ちが固まっていきました。

自分も村田さんのようなおいしいイチゴを作りたい。それを目標に2018年に会社を辞めて家族と共に鉾田に移住し、そこから約3年間、夫婦で研修に入りました。年に1度しか経験できない作業もありますので、全ての仕事を覚えるのに少なくとも2シーズンは必要でした。
植物生理学の勉強をしたり作業工程をパソコンでまとめたり、システマチックに勉強するのは得意なのですが、僕が最も苦手なのが感覚で覚えるということです。しかし良質なイチゴを作るには、とにかく同じ作業を反復して頭と感覚の全てでイチゴを理解する必要がありました。毎日ハウスに通って、観察して、触れて、頭ではなく体で覚える。そうして感覚値を養っていく。本来は苦手なことですが、それが最も重要なことでした。
独立から今日までの日々
−鉾田市で農業研修をし、常陸大宮市で開業されています。なぜこの場所に決めたのでしょうか。
真吾さん:
実習を始めた当初から、いずれは鉾田市内で農場を持ちたいと思い土地探しを始めました。代々畑として使われてきた土地で、平坦で四角く、将来的に規模拡大しやすいところという条件に合う土地がなかなか見つからないまま2年ぐらい過ぎてしまいました。
範囲を広げて土地探しをするようになり、一度契約まで至る土地を見つけましたが、訳あって解約を余儀なくされました。今はもういい勉強になったと言えるようになりましたが、この時のトラブルにはかなり疲弊し、土地との出合いには運や縁が必要なのだと痛感しました。気持ちを切り替えて県北地域に目を向けて、出合ったのがこの三美(みよし)の土地です。

結衣さん:
初めて土地を見にきた時の印象もとても良かったんです。私は海や川に憧れがあって、以前からこの近くに子どもを連れて川遊びに来たりして、気持ちの良い所だなと思っていました。そんな御前山と那珂川が見渡せて、穏やかな風景に平和な時間が流れて。自分たちが暮らす理想のイメージにぴったりの場所だと感じました。
真吾さん:
もちろんデメリットもありました。ここは高台で井戸水が出にくく、御前山ダムから水を引く計画で工事が進んでいました。土地を検討している時はまだ本当にうちまで水が届くかどうかわからない状態で、もし出ないとなれば散水車を購入して毎日水汲みをしないといけない。そんなリスクもあったのですが、それでもここにしようという判断でした。結果的に水が出たので本当に良かったです。

−独立して最初のシーズンで、茨城県いちご経営研究会が主催する「茨城県いちごグランプリ」金賞を受賞されています。初年度から快挙でしたね。
真吾さん:
初年度は村田さんの栽培方法をそのまま踏襲しました。おかげさまでここ常陸大宮でもたくさんの方とのご縁に恵まれ、畑には近くの畜産農家さんから譲っていただく有機質の栄養分が豊富な牛糞を混ぜた堆肥を与えています。その上で太陽熱土壌還元消毒法を行い、健康な土作りをしています。またアブラムシやハダニといった害虫には天敵となる昆虫を利用して防除するなど、できる限り農薬を抑えるための工夫をしています。
しかし土地が変わると気候が変わります。ここは鉾田に比べて気温が低いので、温度管理はこの土地に適した対策をとる必要がありました。土質や水質も変わるので、ベースは村田さんの栽培法を守りつつ、少しずつこの土地にあったやり方を探しているところです。
初年度に8棟のハウスを建てましたが、夫婦二人で管理できたのは6棟が精一杯でした。有り難いことに良質なイチゴが採れて、収穫量12トンからのスタートでした。毎年少しずつ作付けを増やし、4年目の今年は21棟。今はバリ島出身のスタッフが6名いますので、彼らの力を借りて来年は34棟に増やし、総面積はいよいよ1ヘクタールを超える予定です。
生きたいように生きる そのために
−今後の目標として視野に入っていることはありますか。
結衣さん:
今年からイチゴのパッケージを新しくしたところです。表面には私が作った絵本を元にした物語と、そのキャラクターを描きました。
普段からおいしさ重視で厳選したいちごだけを、一つの作品を作るような気持ちで箱に詰めています。そういう思いもお伝えできたらとうれしいと願ってきましたので、オリジナルのこのパッケージができたことで、よりhiko farmらしさを感じていただけるのではないかと期待しています。

真吾さん:
規模拡大の構想やオーガニックのいちご作り、自分たちのライフスタイルに適した経営の仕方など、考えていることはいろいろとありますが、僕らの場合、目標ありきでがむしゃらに数字を達成していくとか、そういうことではないと思っているんです。

彦田家には「生きたいように生きる」というテーマがあります。家族で一緒にいたい。とにかくおいしいいちごを作りたい。優しい人でありたい。そういう根源的なことを優先した先に結果がついてくるのが理想です。
hiko farmのメンバー全体としてのテーマは「レッツ エンジョイ ライフ」。遠く海外から来て働いてくれているスタッフのみんなとも、お互いに尊重しあえる関係でいたい。前向きなエナジーで、楽しんでチームワークしていこうよ。だから勤務評定は能力よりも人間性を尊重しますと伝えていて。要は「優しくていいヤツ」だったらお給料が上がります。みんなそれを理解してくれているので、誰もが気持ちよく働ける、和やかな雰囲気が出ていると思います。

−お話しの節々に村田さんとの共通点を感じます。他にも村田さんから学んだことはありますか。
真吾さん:
まずは会社を辞めて本格的に開業を目指したいと言う僕たちを受け入れてくださったことに、心から感謝しています。ご自身のメリットになるのかどうかわからないのに、イチゴに関するすべてを惜しみなく教えてくださり、人としての器の大きさを感じています。
そのこともあって、僕たちも「ください、ください」ではなく与える人になろうと、日々そう思うようになりました。実際に与える側の人になるには実力はもちろん、経済面などにおいても強さや豊かさが必要です。そのためにも自分たちがまずはしっかりと成長して、余力を持てるようになりたいと思っています。
村田農園での研修当時の様子。前列真ん中が村田さん夫妻。後列左端が彦田さん夫妻(2020年4月撮影)
村田さんの元で学んだことは他にもたくさんありますが、最もたいせつなことは何かと言えば、技術論でもなく経営に長けるための方法でもなく、「おいしいイチゴを作る」ことだと思います。あまりにもシンプルなこたえですが、イチゴ屋として何を一番とするか、イチゴと向き合う村田さんの姿からそのことを学ばせていただきました。
心臓の手術を受けてから今に至るまで、いろいろなものがどんどん削ぎ落とされて、自分たちがどういたいのかということが見えてきた気がしています。それを実行できる環境を与えていただいていることを、とても有り難く思っています。
【取材録】
イチゴは種子による繁殖のほかに栄養繁殖という方法でも子孫を残します。親株から伸びたランナーと呼ばれる枝が地面を這うように伸びて、その先端に小苗が育ちます。鉾田の村田農園という親株から伸びたランナーの一つが常陸大宮の高台に根を下ろしました。栄養繁殖の大きな特徴は、親株と小苗が同じ性質を持つこと。いちご栽培の技術だけでなく、信条までそっくり受け継いでいるようです。
第一に目指すのは、初めて食べた時に衝撃を受けたあのおいしいイチゴの味を作り続けていくこと。なによりもそれが最優先。自分たちらしい生き方でしっかりとした根を張りながら、オリジナリティあふれる花を咲かせるhiko farmです。