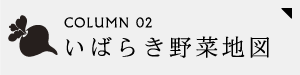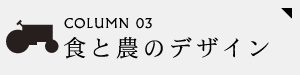昭和34年(1959)に27歳で鯉淵学園を卒業した浅田さん。当時は県内外を問わず就職先はたくさんありましたが、何を根拠に決めれば良いのかわかりませんでした。たまたま農協を案内していただく機会があり、あまり深くは考えず旭村の大谷農協に就職。営農指導員としての道を歩き始めたと言います。
しかし浅田さんがこの職業に就いたのは、根底に父親に反発する気持ちが原動力としてあったからかもしれません。開拓農民として北海道に入植した祖父の仕事を引き継ぎ、旧態依然の労働に明け暮れた父。その姿に疑問をもちながら育った浅田さん。もっと効率的で生産性の高い農業を勉強したい一心で故郷を離れたのですから。
そうしていよいよ学んだことを実践で活かす時が来たわけですが、その頃の浅田さんは農業とどのように向き合おうとしていたのでしょうか。
「大げさなこと言っちゃうけどね、俺は俺なりに感じたことがある。戦争直後の食糧っていうのは、お腹を満たすために、ほとんど澱粉質のものが中心だったわけ。それからタンパク質とかね。でもこれからはビタミンを中心にした農業というかな。俺の知っている先生方や、本でもそう唱えていて、俺もまったくそうだなと共感を持った。つまり人の食生活はその時々で変化するってことだよ。だから時代に合わせて農業も変わっていくものなんだ。それを読み取っていかなくちゃいけない」
浅田さんが農協職員になった当時は、鉾田や行方地区に限らず県西地域に至る広い範囲で、冬は麦、夏は澱粉加工用のさつまいもの生産が主流でした。他には落花生や陸稲などがぽつぽつと作られていた程度だと言います。
そうした時代にはめずらしく、鉾田にはスイカを作る人たちがいました。造谷地区の竹内音次郎さんという方を中心とした20名ほどのグループです。彼らは福島市の中央卸売市場に直接スイカを卸すなど、作るだけでなく販売する感覚も持ち合わせていたようです。後にこのグループが中心となり、新しく開発されたプリンスメロンの試作に取り組むこととなります。
ここでひとまず、当時のメロン事情についてお伝えしておきましょう。
古くから日本で食べられてきたメロンといえば、東洋系品種のマクワウリ(真桑瓜)です。果肉は白く、ハリのある食感で、表皮に網目はなくつるりとしています。路地での大量生産が容易で、手頃な甘味として親しまれてきた庶民の味です。マクワウリに次いで作られていたハネデューメロンやホームランメロンといった品種も網目はなく、東洋系のさっぱりとした甘さで、安価に流通されていました。
一方、網目模様が特徴的で甘味がつよく、果物の王様として位置付けられていたのが西洋系のメロン。本格的に日本で作られるようになったのは、大正14年にイギリスから導入されたアールス・フェボリット種が始まりと言われています。ガラスの温室で栽培される西洋系のマスクメロンは、一流の果物店や百貨店でしかお目にかかれない超のつく高級品。購買層がはっきりと区別され、庶民の口に入ることはありませんでした。
マスクメロンのように甘くておいしいメロンを、もっと手頃な価格で食べたい。多くの人がそう望むなか、いよいよ登場したのがプリンスメロンでした。
プリンスメロンは日本の種苗会社「サカタのタネ」が開発した品種。マクワウリの一種(ニューメロン)と西洋系のスペインメロンの一種(シャランテ)を交配させ、高温多湿な日本の気候でも露地栽培が可能で、たくさん供給できるメロンを目指して研究されました。1961年に完成したプリンスメロンは、糖度が高く、香りもよく、果肉もやわらか。まずは国内の数カ所にて栽培が始められました。
「サカタのタネが最初は全国で何ヶ所か、ここぞというところに、種苗屋さんを通してプリンスメロンのタネを投入していったわけ。この辺りでは山形県酒田市、栃木県真岡市、千葉県富津市、そして茨城県は大洗の増屋種苗さんを経由して、竹内音次郎さんのところへ話が伝わってきた。スイカを作っていた音次郎さんたちのグループが、メロンもやってみようということになった。そしてメロンの普及にあたっては農協を中心にして進めていきたいということで、俺がその役を仰せつかったわけ」
数軒の農家でプリンスメロンの試験栽培が始まりました。できたメロンはマクワウリとは比較にならないほど甘くておいしく、食べた人の心をつかみました。
「これはいける」
収益性の高い園芸作物の指導に取り組んできた浅田さん。プリンスメロンに可能性を見出し、当面の販売目標を1億円と決めました。その時から、生産体制強化のために産地と市場の間を奔走する日々が始まったのです。
当時の栽培方法は現在のようなビニールハウスではなく、麦畑の間に竹を曲げて骨組みを作り、その上にシートを張った小型トンネルの路地栽培でした。保温のためのむしろをかけたり外したりする被覆作業がたいへんな重労働です。それでも作れば売れる人気のプリンスメロン。収益性が高いと聞いて、多くの農家がこぞって作り始めました。しかし浅田さんには、そこに一抹の不安がありました。
「儲かると聞けば誰でも飛びつくからね。黙っていてもどんどん作り手は広がってきたけれど、俺はそれが困っていたの。この人に作ってもらったら良いの採れないんじゃないかな、立派なのできないんじゃないかな、そういう人もいるからね。作る人が何十人に増えてもできるだけ気持ちを揃えて、作った品物を揃えて、たとえ時間がかかっても、そういうやり方がいいと思ったんだ」
プリンスメロンは市場からも高く評価され、短期間に全国各地で栽培への取り組みが始まりました。関東近辺では栃木県真岡市と千葉県富津市が強力なライバルです。
負けず嫌いの浅田さんは、鉾田を日本一のメロンの里にしたい。そのためには品質向上が最大の課題だと考えました。どの産地もスタートラインはほぼ一緒なのですから、いずれ差が出るとしたら要因はそこにあると確信していたのです。
当時はそれぞれの集落ごとに集荷場を設けていました。その数は20ヶ所以上。その場の検査には浅田さんが立ち会いました。ライバルに負けたくない一心で基準を厳しくすると、一部の人たちからは「浅田さんは北海道出身、地元の人間ではないからだ」など、不満や中傷が聞こえてくることもありました。
扱う量が増えてくると、すべての検査を浅田さん一人では手が回りません。本来であれば農協の職員ができれば良いのですが、そう簡単に職員を増やしてはもらえません。そこで、それぞれの集落ごとに農家さんの中から真面目な人を選んで検査を依頼し、品物を揃えてもらうことにしました。それでも出荷の最盛期にはほぼ毎日のように、夜明けまで検査を続け、そのままトラックに乗り込んで東京に向かう日々が続きました。
「ある時こんなこともあったんだ。たまたま巡回に行った集荷場で、見たらどの箱にも秀のハンコが押してある。でも確認したら秀らしいものはないんだよ。これは全部優か良だから、もう一度検査し直してくれ。それが終わるまで俺は帰らないからって言った。そうしたらそこの支部長が接待のために酒なんか出してきてね。そんなのはいい、とにかく検査し直すまで俺は帰らないと言って、優だか良だか全部押し直してもらったのを確認して帰った。その時メロンは2,000箱くらいあったんじゃないかな。ところが、これはずっと後になって、俺が定年してから聞いた話しだけどね。俺が帰った後で全部、また秀のハンコを押し直したっていうんだ。俺、それまで人を疑うようなことはなかったんだけど、あの時は…。時々はそういうこともあったんだな」
その頃は農家の方たちもたいへんでした。各自収穫したメロンを箱詰めし、手作業でクルマに積み、各部落の集荷場まで運びます。次に仲間の中から選ばれた検査員が一箱一箱全部を目視検査し、等階級ごとに積み上げます。それから農協の職員が目揃えをします。
そうしてすべての集荷場で集計が終わると、全体の状況から判断して、どの集荷場からどの等級を何箱、どの市場宛に発送するかが決まります。検査も積み荷作業も、すべて農家の人がやっていたのです。
当時メロン農家の子どもだったという人は、メロンの収穫期になると両親はいつも不在だったと振り返ります。畑作業が終わって箱詰めしたら今度は集荷場に行ってしまい、時には朝まで帰ってこない。その頃は親と一緒に夕飯を食べたことがないと。
浅田さんの功績が記された『20世紀 茨城の群像』にも、不眠不休の出荷時代のことがこう記されています。
======
出荷の最盛期には夜明けまで検査を続け、そのままトラックに乗り込んで東京に向かう日々が続いた。農家から「浅田さんの分だよ」と、差し入れされたおにぎりが身に染みてうれしかったという。
======
「6万箱、7万箱と、何日も続くんだわ。多い時は大型トラックが20台以上。それを積むのにフォークリフトもないし、ベルトコンベアもない。積み終えると農家の人も一緒にトラックに乗って市場まで行ってもらって、荷物を下ろしてから帰ってきた。市場への出荷なんかは農協が先頭をやるだろうけど、でも現在の形になるまでの過程っていうのはね、農家の人たちもそれはたいへんな思いをしながら、一緒になってメロンを盛り上げてきたんだ」
オリンピックが開催された昭和39年(1964)、浅田さんが所属する旭地区の大谷農協と、夏海農協、諏訪農協の3つの農協が合併し、旭村農協(現・JA茨城旭村)が設立されました。その2年後の昭和41年(1966)年にプリンスメロン部会が発足。初年度の会員数は35名、作付面積5ヘクタールからのスタートでした。
翌年の1967年には会員数が115名に増えました。しかしつる割れ病が発生し、自根栽培の限界を確認。耐病性を持つ台木への接木栽培に切り替えました。同時期にメロンに適した肥料の研究を開始。これらが功を奏し、メロンが徐々に安定して採れるようになり、昭和44年(1969年)にはメロン部会の会員数221名、畑は42ヘクタールに増え、売り上げが初めて1億円を超えました。