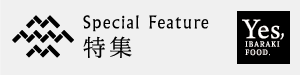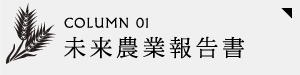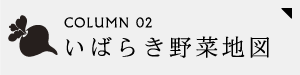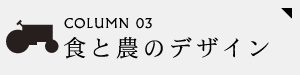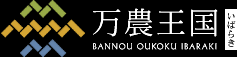「茄子は茄子でしょ?」そう思っていた茨城県八千代町の農家・久保谷さんが、今年初めて作った水茄子を食べて驚きました。「あれ、うまくね?」。
大阪・泉州のブランド品として知られる水茄子が、関東の産地で「とろける万能水茄子」として栽培・出荷をスタートしました。気候変動や市場価格の不安定さに悩む若手農家たちと、30年の市場経験を持つ農業革命株式会社の石橋さんが手を取り、地域の持続可能な農業を生み出そうとしています。
今回は、茨八グループの久保谷さん(久保谷農園代表)、秋葉さん(長茄子栽培歴20年のベテラン農家)、そして農産物市場経験30年のプロフェッショナルとして販売戦略・ブランディング・栽培技術指導などを担当した農業革命株式会社代表取締役の石橋さんにお話を伺いました。
独自の農業グループが育まれる八千代の肥沃な大地
茨城県八千代町は関東平野のほぼ中央、東京から約60kmに位置する人口約2万2000人の町。鬼怒川が運んだ肥沃な土地は「肥土(あくと)」と呼ばれます。平坦で水はけがよく、温暖な気候と相まって農業に最適な環境です。特に白菜は全国一の生産量を誇ります。
八千代町の農業の特徴は、販売ルートの多様性にあります。常総市・下妻市・八千代町の農業関係者を支援するJA常総ひかりだけでなく、独立した組合が存在。農家が自らの判断で販路を選択できる環境が整っています。
このような背景の中で、農業革命株式会社という農産物の流通を手がける会社とともに持続可能な農業の実現を目指す若手農家グループ「茨八グループ」があります。この団体は、2025年から新たに水茄子栽培に挑戦しています。
扱うときは桃のように。大阪で盛んなブランド野菜「水茄子」
水茄子の最大の特徴は、その名前の通り非常に水分量が多いことです。果実を手で絞ると水が滴るほどです。また灰汁(あく)がほとんどなく、皮は薄くやわらかなため、生のまま食べることができます。
大阪府南部の泉州地域で江戸時代から栽培されており、現在では高級ブランド野菜として知られています。価格も一般的な茄子とは大きく異なります。例えば、一般的な長茄子が3〜4本入りで300円程度に比べて、泉州の水茄子は6個入りで1580円程度。長茄子に比べて泉州の水茄子は約5倍の販売価格です。(2025年7月現在の価格、編集部調べ)
水茄子の実は非常にデリケート。皮が薄いため、葉が少し触れただけでも傷がつき、商品価値を損なってしまいます。そのため、桃のような丁寧な管理が求められる、手間のかかる作物でもあります。
白菜日本一のまちで、新たに水茄子作りに挑戦
2025年4月、茨城県八千代町で関東では珍しい水茄子の栽培が始まりました。手がけるのは地元の若手農家グループ「茨八グループ」のメンバーである久保谷さんと秋葉さん。大阪泉州の高級ブランドとして知られる水茄子を、なぜ関東の産地で栽培することになったのでしょうか。気候変動で夏場の葉物野菜栽培が困難になる中、新たな選択肢として「とろける万能水茄子」の挑戦がスタートした背景と現在の状況を聞きました。
—関東地方では珍しい水茄子の栽培を、八千代町で始めたきっかけを教えてください。
久保谷さん:
ここ数年、夏場に栽培してきた葉物野菜の収量が落ち込んでいました。連日の猛暑の影響ですね。経営への影響も見過ごせない中、以前より一緒に仕事をしていた農業革命株式会社の石橋さんに相談したのがはじまりです。
そのときにご提案いただいたのが水茄子。もともと八千代町は茄子の産地でもあり、私たちも長茄子の栽培を始めました。しかし長茄子は、茨城県内はもちろん近隣地域でどこでも作っているから競合が多いです。新しい作物を作るにも、販売先を開拓しなくてはなりません。
そんななか、地域の農業に理解が深いだけでなく、流通販売、宣伝を考えた戦略を考えられる石橋さんから、「水茄子は面白いはず」とアイディアをいただきました。
石橋さん:
関東の方も、水茄子といえば「大阪の泉州水茄子」というイメージはあるんですが、高価ですし、流通量も限られています。
一方、私が30年近く農産物市場を見てきた中で、八千代町は長茄子の名産地ということを知っていました。産地として、土壌や気候の適正はありますし、関東では水茄子を作る農家も販売する流通業者もほとんどいません。まさにブルーオーシャン。先鞭をつけば、茨八グループの皆さんの課題を解決し、持続的な農業の実現につながると思いました。
―食感と使い勝手が想像できる「とろける万能水茄子」というネーミング。この由来は何ですか?
石橋さん:
「水茄子といえば浅漬け」のイメージが強く、食べ方はほぼ一択、のような印象がありました。でも実際に試してみると、炒め物でも揚げ物でも、生でカプレーゼのようにしてもおいしい。いろいろな料理で楽しめるところから「万能」とつけました。「とろける」は水分量が多く皮が薄いので、特に火を通すと口の中でとろけるような食感になることから。ただ水茄子というよりも、「とろける万能水茄子」と言ったほうが、味や食べ方の想像が膨らみます。お客様の頭の中の選択肢を増やして、もっと気軽に買ってもらえるようにしたかったんです。
—現在、どれぐらいの量が栽培・出荷されているのでしょうか?
久保谷さん:
2025年4月28日に初めての作付けをして、約1ヶ月半で初収穫を迎えました。圃場面積は2反ほど。現在は週3回のペースで、大人の握りこぶし大になった実を収穫して、1日あたり900kgほど出荷しています。実の成長スピードはとても速いですね。朝5時からの収穫を終えて、夕方改めて畑を見に来ると、枝に残した小さな実が、翌日には収穫できそうなぐらい大きくなっているので驚きます。今年が水茄子栽培の初年度なので、これからどうなっていくか楽しみです。長茄子栽培の経験を生かして、おいしい水茄子を作っていければと思っています。
石橋さん:
現在は、東京23区内を中心に展開するスーパーマーケットチェーンを中心に出荷しています。スーパーマーケットのバイヤーの方々も水茄子について詳しく知らない部分があります。茨八グループがおいしく育てた水茄子を、きちんと消費者にお届けし喜んでいただくために、水茄子の歴史や食べ方をレクチャーしながら販売を進めています。
互いに補いあい地域ネットワークを生かす「茨八グループ」とは
久保谷さん、秋葉さんをはじめ茨城県八千代町の若手農家5人が4年前に結成した「茨八グループ」。農業では、農産物を市場に出荷した際の価格は、需要と供給のバランスで決まります。そのため同じ野菜でも日によって価格が大きく変動します。価格の不安定さという課題を解決し、持続可能な農業を実現するために、地域の農家が集まり結成されました。栽培作物の相互補完的な関係を築き、独立した販売ルートを開拓し、地域ネットワークを活かした持続可能な農業経営を目指す取り組みと、グループ運営の実際について詳しく話を聞きました。
—茨八グループとはどのような組織なのでしょうか?
久保谷さん:
4年前に結成した、40代を中心とする若手農家5人による共同出荷販売グループです。40代といっても、先輩たちの層の厚い農業の世界では、まだまだ若者扱いですね。メンバーはみんな茨城県八千代町の農家。茨城と八千代の頭文字をとって「茨八(いばはち)」という名前にしました。白菜、キャベツ、ネギ、小ネギ、ピーマン、長茄子、チンゲンサイ、春菊、メロン、そして水茄子など、メンバーそれぞれが異なる作物を栽培しています。
秋葉さん:
それぞれの農家で違う強みを持っています。お互いに補完し合いながら、お客様にいつでもおいしい野菜をご提供できるようになっています。例えば、レタスしか作ってない農家にお客様から白菜の注文をいただいたとき、グループ内の白菜農家から供給できます。地域ネットワークを生かしたグループだからこその強みですね。
—グループを結成した理由を教えてください。
久保谷さん:
一番の理由は価格の安定化です。市場出荷だと、同じ野菜でも1,000円になるか200円になるか、その日の需給バランスで全く予想がつきません。農家には、どんなに良い野菜を作っても収入が安定しないという大きな問題がありました。
農業は人々が生きていくうえで欠かせない事業ですが、収入の不安定さは、私たちだけでなく、次の世代にとっても不安の種。だからこそ、なるべく価格が安定した状態で販売ができればと思い、グループを結成しました。
結成当初から比べると、徐々に実績を積んで、今では安定した販売ができるようになってきました。販売を自分で行うため、出荷後の収益の予想もしやすくなり、経営計画も立てやすくなりました。
作るプロと販売のプロ。農業革命株式会社とのパートナーシップ
茨八グループの転機となったのが、農業革命株式会社代表の石橋さんとの出会いでした。農業革命株式会社は、農産物の流通・販売・ブランディングなどを手がける会社。生産者と小売店・飲食店などの間に立って、付加価値の高い農産物の販売をサポートしています。市場経験30年の石橋さんは、生産者と販売者両方の視点を持つ稀有な存在です。
石橋さんと茨八グループは、「とろとろ白菜」プロジェクトでの成功を経て信頼関係を築き、水茄子栽培につながりました。単なる売買関係を超えた深いパートナーシップは、どのように形成され、どんな価値を生み出しているのでしょうか。
—石橋さんと茨八グループの出会いのきっかけを教えてください。
石橋さん:
4年前に人づての紹介で茨八グループと出会いました。農家さんたちが課題を抱えていることは理解しながらも、自分はどのように役に立てるのだろうか?と考えていたときに見かけたのが、久保谷さんの庭先で栽培されていた「新理想白菜」。新理想白菜は非常に柔らかくておいしい品種。まずはここからスタートしようと思い、「とろとろ白菜」の商品開発が始まりました。
久保谷さん:
自分としては新理想白菜のおいしさを理解していましたし、火を通すことで甘く柔らかくなるとろとろ白菜には自信を持っていました。
でも実は「白菜は白菜だし、本当に売れるのかな」という感覚もありました。一般の消費者の方は白菜を食べ比べる機会がないので、いくらおいしく作っても、違いを分かってもらえないと思っていたんです。
—信頼関係はどのように築かれていったのでしょうか?
石橋さん:
茨八グループの皆さんは、プロとして安心・安全でおいしい野菜を作ってくれる。一方私は、広報や販売、ブランディングの側面からプロとしての仕事に取り組みました。
ただ名前をつけて売るだけではなく「きちんと宣伝する」ことも重要で、ここに力を入れました。なぜ八千代の新理想白菜はおいしいのか、とろとろ白菜の魅力は何か?などを伝える必要があります。
とろとろ白菜は、私が茨八グループから仕入れ、スーパーマーケットなどに流通させます。このときは、より商品の魅力を伝えるために、仕入れ価格を少しだけ安くさせていただき、余剰金額をWebサイト、パッケージ、チラシなどの広告宣伝費として使わせていただきました。
安くなった分は、私の懐に入るのではなく、たくさんの人たちにアプローチするための費用となる。費用対効果の高い投資だということも、しっかり説明させていただきました。
久保谷さん:
石橋さんからは、販売や広報の視点での説明があり、私もなるほどなと納得できました。
宣伝効果は大きく、実際にとろとろ白菜は、2年目の2024年にテレビ番組『満天☆青空レストラン』に取り上げられて、爆発的に売れました。確かな成功事例ですし、作り手としても自信につながりましたね。実績はもちろんですが、石橋さんは、私たちが大切に育てた白菜のために一生懸命になってくれたからこそ、お互いの信頼関係がより一層深まったと思います。
―作る人と広める人のタッグには、どのような特徴があるのでしょうか?
石橋さん:
僕は30年近くこの業界にいて、前半は市場で農産物を小売店に販売する業者「仲卸」として販売の現場を、後半は生産者の支援を続けてきました。生産者のことも売る側のこともわかります。そのため、うまく間に入って微調整をして、両者が損をせずに農産物が流れるような仕組みを作ることができます。
久保谷さん:
とろとろ白菜の成功や、水茄子の手ごたえもあって、「石橋さんが間に立ってくれるから、きっと上手くいく」という安心感があります。フランクな方ですが、わざわざ八千代町まで足を運んで一緒に汗をかいてくれるので心強いです。
栽培から販売まで全体を見て、売り方も含めてサポートしてくれる強みがあるので、私たち農家は作ることに集中できる。とても助かっています。猛暑で葉物野菜が不作になったときも、「一緒にきちんと売れるおいしい野菜を作りたい」と思いながら相談ができました。
石橋さん:
単なる農産物の売買関係ではなく、深い関係性の中で取り組ませていただいているつもりです。生産者の家族の生活やいろんなものを背負っているという責任感を持って、しっかりと結果を出すことを大切にしています。
作り手もバイヤーも自信をもってオススメできる水茄子づくり
デリケートな水茄子の栽培には、長茄子とは異なる細やかな技術が求められます。乳酸菌堆肥による土づくりから、シビアな水分管理、桃のような丁寧な収穫・出荷作業まで。品質の高い水茄子を安定して生産するための工夫の数々があります。石橋さんの知見と茨八グループの栽培技術が融合した、こだわりの栽培方法について具体的に聞きました。
―おいしい水茄子を作るための、独自の工夫はありますか?
久保谷さん:
基本的な茄子の栽培方法に加えて、乳酸菌の堆肥を入れてしっかりと土作りをしています。牛の餌に乳酸菌を混ぜて、その牛の堆肥を使用する方法です。通常の堆肥よりも微生物が豊富で、土の中の環境が良くなります。
久保谷さん:
水茄子の圃場には、ところどころにマリーゴールドが咲いています。虫を寄せ付けない効果が期待でき、農薬の使用量削減にもつながります。
石橋さん:
水茄子の栽培で使ったのは、乳酸菌を使った堆肥。栃木県大田原市のアスパラ農家でも、その効果が実証されており、例えば病気が抑制されたり、農薬などの資材を買うコストが低減されたりしています。さらに、収量が年々上がり、4年で倍になったという結果も出ています。
この肥料を使った茨八グループの水茄子も、初年度からなかなかよい収穫量と品質となりました。今シーズンいっぱい、そして来年以降も、きっといい結果が出ると期待しています。
―今年も猛暑が予想されますが、栽培管理で特に気をつけていることはありますか?
久保谷さん:
水分管理が最も重要です。夏場は暑いだけでなく乾燥がひどいので、マルチ(畝を覆うビニールシート)の下にチューブを通して、地面が乾いたらすぐに水を与えています。実は乾燥すると艶がなくなってしまいますし、一度悪くなると、そこから回復するのはとても難しい。収穫のたびに株の様子を見て、葉の状態や土の乾き具合を確認しながら適度に調整しています。水やりは自動化されているわけではないので、常に気が抜けないですね。
石橋さん:
水をやりすぎても根腐れを起こしたり、逆に病気の原因になったりします。気温、圃場、水茄子のコンディションを見ながら感覚的に行う必要があります。プロが持つ長年の経験が物を言う作業ですね。
―デリケートな水茄子。栽培や出荷時の品質管理で気を付けていることはありますか?
久保谷さん:
皮が非常に柔らかいので、収穫時は普通のゴム手袋ではなく、軍手を使用しています。また、実に葉が触れて傷がつかないよう、こまめに葉を剪定しています。収穫したナスは薄いスポンジの上に並べるなど、桃や高級果物のような扱いで出荷作業を行っています。実の表面に手の跡がついてしまうようなことも絶対に避けたいですね。
石橋さん:
おいしい水茄子も、やはり最初は見た目から入ります。スーパーマーケットのバイヤーや仲卸の方々も、厳しくチェックされます。表面がキラキラしているか、傷がないか、ヘタの色はどうかといったところが、消費者に届くまでの第一関門。そこをクリアして、実際に食べて、おいしい!と思っていただいて、やっと消費者から良い評価をいただけます。
八千代町の新たな名産「とろける万能水茄子」の展開
従来の水茄子といえば浅漬けが定番。しかし「とろける万能水茄子」は炒め物、揚げ物、生食まで幅広い調理法に対応します。実際に秋葉さんのご家族が作った多彩な料理を試食しながら、その可能性を実感しました。販売戦略から将来の地域展開まで、関東発の新しい水茄子ブランドが目指す未来について、作り手と売り手それぞれの想いを聞きました。
―「万能」な水茄子の、おいしい食べ方を教えてください。
秋葉さん:
我が家では、妻にいろいろと水茄子料理を作ってもらっています。チーズ焼き、肉巻き、カプレーゼ風、フライ、揚げ浸しなど本当に多彩です。水分が多い野菜ですが、焼いても揚げてもおいしい。まさに「水茄子のフルコース」が楽しめますね。水茄子は皮が薄くて柔らかいので、皮ごとおいしく食べられます。生ハムメロンならぬ「生ハム水茄子」もオススメですよ。
久保谷さん:
実は、最初は「水茄子と言っても、茄子は茄子でしょ」みたいな感覚だったんですよね。でも実際に食べてみたら「あれ、うまくね?」と驚きました。私は調理師の免許を持っていることもあって、いろいろな料理を試して楽しんでいます。毎日のおかずにはもちろん、お酒のおつまみにもピッタリですね。
―さまざまな食べ方を楽しめる水茄子。これからどのように消費者のもとに広めていくのでしょうか?
石橋さん:
やはり、まずは多様な食べ方を伝えることが重要です。スーパーマーケットのバイヤーの方々も水茄子について詳しく知らない場合が多いです。おいしいだけでなく、「どうすればご家庭で美味しく食べられるか」を具体的に伝えられないと、今までなじみが薄かった食材に手が伸びづらいですからね。特設したウェブサイトでもいろいろなレシピを紹介しています。
飲食店向けにも、例えば「乳酸菌堆肥たっぷりの畑で育てた水茄子の天ぷら」のようなメニュー提案をして、付加価値を高める工夫をしています。
流通面では、現在は15キロ箱に詰めて出荷していますが、将来的には5キロ箱での出荷を検討しています。店舗の立地や客層によって売れる量が違います。小分けな5キロサイズの箱なら、バイヤーの方々が臨機応変に店舗に並べることが可能。とろける万能水茄子がより多くの消費者にリーチするようにしていきたいです。

写真=左から、久保谷さん、石橋さん、農業革命(株)webマーケティング部の藤村さん、秋葉さん
―八千代町の農業の新たな可能性を見出した今、これからの展開についてお聞かせください。
石橋さん:
とろける万能水茄子をはじめ、茨八グループの皆さんが作る農産物が消費者に喜ばれて売上につながり、関わる全ての人が幸せになったらいいなと思います。
そのために、まずは茨八グループ代表の久保谷さんに、地域で飛びぬけた存在になってもらいたいですね。技術や収益性があるだけでなく、個人ではなくチームとして持続可能な農業を実現する体制をつくり、周りの農家とも連携して一緒に事業を営む形ができれば、地域全体が盛り上がっていきます。そして販売先が広がれば、農産物を食べて幸せな気持ちになる家族がもっと増えます。
農家が作り、きちんと販売され、消費者が喜ぶ。そして作り手である農家もうれしくなる。そんな幸せの循環を作りたいですね。
久保谷さん:
今まで市場出荷で毎年の売り上げが大きくばらついていました。安定した価格で販売できれば、たとえば銀行からの借り入れに頼りがちだった農業からも脱却できます。収益が安定すれば、資金を設備投資に回したり、圃場を広げたり、雇用を生み出したりすることも可能なはず。
何より、自分たちの子どもに「農業はきちんと稼げる仕事」「魅力的な仕事」と感じてもらえる仕事に出来るのではないかと思います。
石橋さん、茨八グループの仲間たち、そしてなにより地域の人たちと一緒に、おいしい作物をみなさまに届けながら、次世代も「農業っていいな」と思えるような環境を作りたいですね。
■とろける万能水茄子 特設ページ
【取材録】
農業革命株式会社
東京都大田区東海3-9-11 SRKビル2F
TEL.03-6303-6710
https://www.revocompany.co.jp